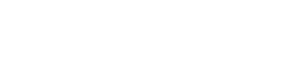ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学 ⑲
Part4 最先端の組織学習論
第8章 組織の学習力を高めるには、「タバコ部屋」が欠かせない
前章まで、イノベーションを生み出すために必要なことについて、最先端の経営学の知見を
紹介しました。
例えば、社員一人ひとりが、幅広い知を探索して、それを新しく組み合わせることなどが
それにあたります。
本章からはさらに踏み込んで、「企業はこの探索した知をどう活用して、学習すべきか」に
ついて考えてみましょう。
そのための第一歩は、情報の共有化です。
各社員が持っている知を「新しく組み合わせる」には、企業内において社員が、その知を
共有している必要があります。
この情報の共有化あるいは「組織の記憶力」において、最先端の組織学習研究で重要視
されているのが、トランザクティブ・メモリーという考えです。
本章ではトランザクティブ・メモリーを紹介しながら、日本企業への示唆を考えていきましょう。
✔️ 大事なのは「情報の共有化」ではない
トランザクティブ・メモリーは、世界の組織学習研究ではきわめて重要なコンセプトと
位置づけられています。その要点は、組織の学習効果、パフォーマンスを高めるために
大事なのは、「組織のメンバー全員が同じことを知っている」ことではなく、
「組織のメンバーが『ほかのメンバーの誰が何を知っているのか』を知っておくことである」と
いうものです。
英語で言えば、組織に必要なのはWhatではなく、Who knows What である、ということです。
よくビジネス誌などで「情報の共有化」という言葉が使われます。
そして多くの方は、情報の共有化とは、「組織のメンバー全員が同じことを知っている
ことである」と認識されているはずです。しかし考えてみてください。
ヒト一人の知識のキャパシティには限界があります。
それなのに全員が同じことを覚えていては、効率が悪いはずです。
組織の本来の強みとは、メンバー一人ひとりが、マーケティングの人なら商品の知識、
開発者なら技術の知識、法務の人は法律の知識、ある営業は顧客Aの知識、別の営業は顧客Bの
知識と、それぞれの専門知識を持って、それを組織として組み合わせることにあるはずです。
他方で、その専門知識がいざ必要なときに、組織として引き出せなければ意味がありません。
したがって組織に重要なことは、いざとなったときに「あの部署の◯◯さんならこのことを
知っているから、そこで話を聞けばいい」というWho knows Whatが組織全体に浸透している
ことなのです。
✔️ トランザクティブ・メモリーはパフォーマンスを高める
※ 省略致しますので、購読にてお願い致します。
✔️ 大事なのはメール・電話か、直接対話か
※ 省略致しますので、購読にてお願い致します。
ルイスは、これらの情報を基に統計分析をしました。
その結果からは、まず「トランザクティブ・メモリーが高いチームほどプロジェクトの
パフォーマンスが高い」という結果が得られました。
これは、他の多くの研究と同じ結果です。
注目すべきは、もう一方の結果です。では、どのようなチームがトランザクティブ・
メモリーを高めているかというと、それは「直接対話によるコミュニケーションの頻度が
多いチーム」に限られたのです。
それどころか結果の一部からは、「メール・電話によるコミュニケーションが多いことは、
むしろ事後的なトランザクティブ・メモリーの発達を妨げる」可能性も示されました。
✔️ 「目は口ほどにものを言う」のは本当である
※ 省略致しますので、購読にてお願い致します。
みなさんは、この3種類のカップルの共同作業の成果はどうなったと思いますか。
まず、3タイプの中でパフォーマンスが最も低かったカップルは、(2)になりました。
これは興味深い結果ではないでしょうか。「(2)互いの顔は見えないが、会話はできる」状態は、
「(3)会話はできないが、顔を見ながら文書交換できる」状態より、パフォーマンスは
悪くなるのです。さらに、(1)と(3)のタイプでは、作業のパフォーマンスに違いはありませんでした。
この結果をもって、ホリングスヘッドは、目と目を合わせる「アイコンタクト」や
顔の表情を通じてのコミュニケーションが、トランザクティブ・メモリーを高める効果を
主張します。例えばカップルやグループが、何かこれまでに経験のない課題や疑問に
遭遇した時、彼らは言葉以上に互いの表情や目を見ることで、「誰が何を知っているか」を
即時に判断するのではないか、というものです。
まさに「目は口ほどにものを言う」ということです。
この続きは、次回に。