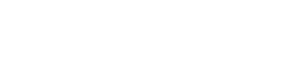続「道をひらく」松下幸之助 ㊿+6
● 自分と他人
もみじの手に澄んだひとみのかわいいわが子。そのかわいいところは
みんな自分に似ているように思えて、わが子が笑えば自分も笑い、舌を
出せば舌を出し、顔をしかめれば思わずこちらもヒョットコ面。
まさにわが分身。時のたつのも忘れてしまう。
それもやがては成長する。そして、一人の人間としての芽生えのなかで、
親の意にそぐわぬふるまいがはじまってくる。何とまあ聞きわけのない
この子と憎らしくもすら思うけれども、よく考えてみれば、そのガンコ
なところもみんな自分に似ているように思えて、文句を言いながらも、
そこにわが影を見る思い。
親子だけではない。他人とても同じこと。他人も人間。神でもなければ
鬼でもない。同じ人間ならば、他人もわが分身。わが影。そのすぐれた
ところはわが内にもあり、その劣れるところもまたわが内にある。
時に口ゲンカをしながらも、親子に切って切れぬ情愛があるように、
時にきびしくその非を責めつつも、切って切れぬ人間としての情愛を
自他のなかで抱きつづけたい。
他人は他人でない。他人も自分である。
● 自然の声
秋の夜。床に入って静かに眼をつむる。とりとめもなき想いが、あら
われては消え、消えてはあらわれる。月に流れゆく雲のような想い。
そんな想いがフト中断したとき、どこからかかすかに虫の声。
チリリリリ。いつのまに鳴いていたのか。この虫の声、自然の声。
なぜ今まで気がつかなかったのだろう。起き上がって窓をあければ、
ヒヤリとした大気のなかに、秋の夜の月。思うこともなくその月を
仰いでいると、虫の声とともに、月光の声もきこえてくるようだ。
サラサラというのだろうか、シンシンというのだろうか。
自然はささやいている。語りかけている。しかしわが想いにとらわれ
ているときには、この声は耳に入らぬ。
心を静めよ。とらわれを捨て切れ。そして耳をすまそう。何も考えずに
耳をすまそう。そのとき、自然の声がわが心につたわってくる。
それはあるいは、赤ん坊のときの汚れのないきれいな自分の本心の
ささやきかも知れない。
狂乱の巷のあゆみをしばしとどめて、秋の夜に身をゆだねてみたい。
心をゆだねてみたい。
この続きは、次回に。