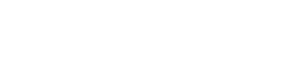P・F・ドラッカー「創造する経営者」㉒
例外はある。例えば、本質的に一種類しかない事業である。
GMの生産物のほとんどは自動車である。そこで同社は、操業度八○%を
前提として、工場で発生した総コストを生産台数で割ることによって一台
当たりのコストを計算している。
もちろんこの計算も一種の一般化ではあるが概念的には間違っていない。
また、海運会社の船舶や航空会社のジェット機など、際立って大きな
コストセンターが存在する場合も、コストは容易に把握できるし、
そのまま利用できる。
しかしそれらの場合を除き、コストの計算は簡単ではない。
われわれは現実のコストを見ていかなければならない。明確な焦点の
ない事業のコストは、作業量による配分が最も現実に近い唯一の計算と
なる。今日の企業活動のコストのほとんどがそのようなコストである。
まず、製品コストのうち通常きわめて明白なものとされているコストが、
実は利益への貢献やコストの負担を分析するには不適切である。
すなわち原材料と部品の購入費である。
ここに、トースター、コーヒーメーカー、アイロンなど小型電気器具の
メーカーの例がある。製品Aの原材料費と部品費は出荷価格の六○%で
あって、製品Bのそれは三○%である。
A、Bの売上高は同じあって、しかも利益率はともに一○%である。
したがって業績は同じと考えられている。
しかし実際には、製品Aでは一ドルの利益をあげるには、自社の資源と
事業費三ドルを必要とし製品Bでは六ドルを必要とする。
さらにここで、製品A、Bとともに、増産しても同じ価格で売れるものとし、
しかもいずれか一方しか増産できないものとする。その場合、製品Aに
同じだけの自社の資源を追加投入することによって、製品Bの場合よりも
二倍の追加生産を行えることになる。製品Aの追加生産に、三○ドル分の
自社の資源と事業費が必要であるとするならば、製品Bには六○ドルを
必要とするからである。
製品Aの増産のほうが製品Bの増産よりも二倍の利益をあげられる。
したがって製品別の純利益やコストを計算するにあたっては、総売上高や
総コストから外部調達の原材料費と部品費を引いた付加価値の数字を使う
必要がある。
利益率(利幅)という概念さえ利益の要因の一つにすぎない。利益は利幅に
回転率を掛けたものだからである。
ここに二種の製品があって、価格がともに一○ドル、原材料費が同額で
あり、利益率がともに一五%であるとする。しかし同一の期間内に、
一方は五単位生産して販売でき、他方は一単位しか生産して販売できないと
すれば、前者は後者の五倍の利益をあげられることになる。
これは初歩的なことである。しかし利益率と回転率という二つの数字が
同時に手元にないときには、このことは容易に忘れられる。
例えば、よく知られているのはデュポンが使っているROI(投資収益率)で
ある。本書の分析で使っている利益の概念や数度はすべて利益率と回転率とを
含むものである。また、生産高とは関係なく発生するコストも計算から
除外しなければならない。それらのコストこそ真の固定費である。
すなわち賃借料、資産税、保険料、維持費、さらには過去の投資に関わる
コストである。もちろん固定費が高率の場合には、海上輸送の例について
後述するように、別途コストの配分が必要となる。
この続きは、次回に。