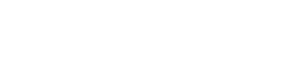P・F・ドラッカー「創造する経営者」㉛
✳️ COLUMN2
1つの計算を例示することによって、これまで述べてきた概念の使い方を
まとめておきたい。ある缶メーカーが、3つの種類の製品、例えば金属製の
缶を生産しているとする。このメーカーの総売上高は1億5000万ドルである。
原材料費は5000万ドルであって純売上高は1億ドルとなる。
固定費は年間3000万ドルであり、したがって総企業利益は7000万ドルと
なる。
製品Xの製品別売上高は4000万ドルであって、原材料費はほかの製品よりも
割合が小さく1000万ドルである。したがって製品別売上高は3000万ドル、
すなわち企業の純売上高の30%である。
そこで製品別売上総利益は、総売上高1億5000万ドルから原材料費5000万
ドルと固定費3000万ドルを引いた総企業利益7000万ドルの30%である
から、2100万ドルとなる。
他方、このメーカーの総コストは1億3500万ドルである。
ここから原材料費5000万ドルと固定費3000万ドルを引いた5500万ドルが
製品別配分コストの合計となる。
このメーカーにおいてコストを発生させている最も代表的な作業は出荷
である。その量は年間25万件である。そのうち製品Xの出荷は、サンプル
調査によって6万件、すなわち全体の24%であることが明らかになったと
する。ということは、5500万ドルの24%に相当する1320万ドルが、製品Xに
配分されるべきコスト(製品別配分コスト)である。
すなわち製品Xの製品別貢献利益は、製品別売上総利益2100万ドルから
製品別配分コスト1320万ドルを引いた780万ドルである。
これは、総売上高1億5000万ドルから総コスト1億3500万ドルを引いた
会社全体の法人税控除前純利益1500万ドルの2分の1を超える額である。
これに対し、製品Yの製品別売上総利益は、総企業利益7000万ドルの
22%、1540万ドルである。しかし製品Yに伴う作業は会社全体の30%で
あって、製品別配分コスト合計5500万ドルの30%は1650万ドルである。
したがって製品Yの製品別貢献利益は、製品別売上総利益1540万ドルから
製品別配分コスト1650万ドルを引いて110万ドルの赤字となる。
さらに製品Zは製品別売上総利益が総企業利益の18%、1260万ドルであり、
製品別配分コストが全体の約29%、1600万ドルである。
したがって製品Zは差し引き340万ドルの赤字である。
このメーカーでは、固定費はかなり高くなっている。そして、ここで示した
数字はこの固定費を計算に入れている。ということは、3つの製品とも
固定費負担を入れて製品別貢献利益を計算しているということである。
したがって、たとえ製品YおよびZのいずれもが赤字であってコストを回収
することができなくとも、両製品とも生産しないよりは生産したほうが
よいということがありうる。
もちろんその場合は、赤字額が固定費の負担分よりも小さく、かつ代わりに
生産、販売すべき収益性の高い製品が存在しないことを条件とする。
この2つの条件のうち特に後者が重要である。後者については、口では
いっても実際に計算することはほとんどないからである。
口ではいっても実際に計算することはほとんどないからである。
固定費をカバーしていればよいとの説は、往々にして無原則な製品擁護論
として使われやすい。製品別の固定費負担は、各製品の製品別総売上高
あるいは製品別配分コストのいずれに比例させてもよい。
私自身は後者を薦める。後者のほうがより論理的であり、かつ弱い製品を
厳しくチェックするからである。
いずれの方法によって計算しても、製品YおよびZは固定費を吸収する
ことによって会社全体の利益に貢献している。しかし製品Zはようやく
合格というところである。
この続きは、次回に。