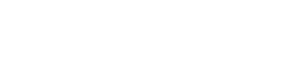ピーター・F・ドラッカー「経営者の条件」⑫
P.F. Drucker Eternal Collection 1
The Effective Executive
Chapter:1
第1章❖成果をあげる能力は修得できる
□ 成果をあげる者はなぜ必要か
成果をあげることがエグゼクティブの仕事である。成果をあげるという
ことは、物事をなすということである。企業、病院、政府機関、労働組合、
軍のいずれにあろうとも、エグゼクティブは常に、なすべきことをなす
ことを期待される。すなわち成果をあげることを期待される。
それにもかかわらず、物事をなすべき者のうち大きな成果をあげている
者は少ない。知力は当然ある。想像力も豊富にある。知識の水準も高い。
しかし、知力、想像力、知識と、成果をあげることとの間には、ほとんど
関係がないかのようである。
頭の良い者がしばしばあきれるほど成果をあげられない。
彼らは頭のよさがそのまま成果に結びつくわけではないことを知らない。
頭のよさが成果に結びつくのは体系的な作業を通じてのみであることを
知らない。逆に、あらゆる知識に成果をあげる地道な人たちがいる。
頭のよい者がしばしば創造性と混同する熱気と繁忙の中で駆け回っている
間に、寓話の亀のように一歩一歩進み先に目標に達する。
知力や想像力や知識は、あくまでも基礎的資質である。それらの資質を
結果に結びつけるには、成果をあげるための能力が必要である。
知力や想像力や知識は、限界を設定するだけである。
これらのことは当然明らかなはずである。しかしそれならば、物事をなす
べき者の仕事の一つひとつについて山ほどの本や論文が出ている時代に、
なぜ成果をあげることはずっと放置されてきたのか。
理由の一つは、成果をあげることが組織に働く知識労働者に特有の能力
だからである。ごく最近まで、そのような立場にある知識労働者はわずか
しかいなかった。
肉体労働者は能率をあげればよい。なすべきことを判断してそれをなす
能力ではなく、決められたことを正しく行う能力があればよい。
なすべきことを判断してそれをなす能力ではなく、決められたことを正しく
行う能力があればよい。肉体労働者の仕事は、靴のような生産物の量と
質で評価できる。
われわれはすでに、それらの方法についてはこの一○○年間に多くを
学んできた。その結果、肉体労働の生産性を大幅に向上させた。
かつては、機械工や兵士など肉体労働者が圧倒的に多数だった。
成果をあげるべき者、すなわち他の者に指示する者はあまりいらなかった。
その数があまりに少なかったため、成果をあげることは、その是非は
別として当たり前のこととしてすまされていた。
そのようなことは、生まれつき素質を身につけているはずの少数の人、
すなわち、ほかの人間が苦労して学ばなければならないことを、なぜか
生まれつき知っているに違いないと思われる少数の人をあてにすることが
できた。
このことは企業や軍隊に限ったことではなかった。南北戦争時の政府は、
今日では信じられないほど小さかった。北部政府戦争省の文官は五○人に
満たず、そのほとんどは、物事をなすべき者や決定を行うべき者ではなく、
通信係だった。一九○○年頃、セオドア・ローズヴェルト時代の連邦政府は、
今日の政府庁舎の一つに収容できた。
ひと昔前の病院には、X線技師、検査技師、理学療法士、栄養士、セラ
ピスト、ソーシャルワーカーなど、今日の病院が患者一○○人に対し、
二五○人も抱えている各種医療サービスの専門家はいなかった。
当時は、わずかの看護師、清掃作業員、料理人、付添人がいるだけだった。
看護師を助手とする医師が唯一の知識労働者だった。
したがって、最近にいたるまで、いわれたことをする肉体労働者の能率の
向上が、組織にとって最も重要な問題だった。
知識労働者は支配的な存在とはなっていなかった。
しかも昔は、知識労働者のうち組織に属している者がごくわずかだった。
彼らのほとんどは、せいぜい助手を一人抱えるだけで、自由業として
独立して仕事をしていた。成果をあげようがあげまいが、彼ら個人の
問題であって彼らだけに関係のあることだった。
今日では、知識を基盤とする組織が社会の中心である。
現代社会は組織の社会である。それら組織のすべてにおいて中心的な存在は、
筋力ではなく頭脳を用いて仕事をする知識労働者である。
知識や理論を使うよう学校で教育を受けた人たちのますます多くが組織で
働いている。彼らは組織に貢献して初めて成果をあげることができる。
そのような社会では、もはや成果をあげることを当然のこととすることは
できない。軽く扱うわけにはいかない。
この続きは、次回に。