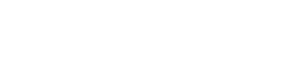書籍「Effectuation エフェクチュエーション」 ㉟
✔︎ コーゼーションとエフェクチュエーションの使い分け
ただし、ほとんどの民間旅客機にオートパイロットシステムとパイロットの両方が存在
するように、コーゼーションとエフェクチュエーションは、どちらか一方があらゆる
状況で有効であるわけではなく、両方を状況に応じて使い分けるべきであるといえます。
すでに述べた3つの条件を伴う問題空間においては、パイロットが自らコントロールに
集中するエフェクチュエーションが求められるが、起業家の目的が明確に定義されたり、
環境が安定してさまざまな分析を通じてアプローチが予測できる状況へと変化する
ならば、コーゼーションもまた十分に有効な意思決定の論理となるでしょう。
実際に、エフェクチュエーションを提唱したサラスバシーも、「その企業が生き残り、
成長するにつれて、特にその企業が創出した新たな市場をさらに活用し、長期での競争
優位を構築するためには、その企業のマネジメントはよりコーゼーションに基づくものに
なっていく必要がある」と述べ、企業のライフサイクルに伴い、どちらの論理を用いる
かが変化することを想定しています。
つまり、起業家が新たな事業に着手した段階では、市場も企業もいまだ存在しませんし、
未来の予測可能性はほぼゼロに等しいため、必然的にコントロール重視の戦略を選択
することになります。とりわけ活用できる資源に制約がある場合には、起業家の意思
決定はよりエフェクチュエーションに偏重したものとなるでしょう。ただし、そのスタ
ートアップが、たとえばベンチャーキャピタルなどの公式のステークホルダーを説得
する段階になると、何らかの将来予測に基づいた事業計画の策定を求められることも
あるでしょう。さらに、事業が成功した結果、その企業が生み出した新たな市場が安定
する段階になると、市場分析と予測的な情報に基づいた計画的な経営が可能になると
期待されます。このように、長期にわたって存続する企業では、そのライフサイクルの
どこかの時点で、エフェクチュエーションが優勢なモードからコーゼーションが優勢な
モードへ、変化していくことが考えられます。
ただし、こうしたコーゼーションによるアプローチで成長して大企業となった組織が、
その後もよりコーゼーション偏重で存続できるとは限りません。その企業が生み出した
新しい市場が成熟する段階になると、他社が開発をした革新的新製品が登場するなどして、
環境における不確実性が再び高まる可能性があるためです。そうした状況で、予測合理
性のみを重視した意思決定をし続ける企業には脆弱性が生じ、エフェクチュエーション
に基づいてまったく新しい技術や製品を生み出す別の企業の台頭により、それまでの
事業基盤を一気に失ってしまう恐れもあるでしょう。つまり、市場の成熟期には、
大企業も再びエフェクチュエーションを活用して、新たな事業機会を創造していく必要に
迫られるのです。
コーゼーションとエフェクチュエーションの関係については、サラスパシーが最初に
発表した論文のなかでも、「コーゼーション的推論とエフェクチュエーション的推論は、
常に逆方向に作用するわけではなく、むしろ両者は補完的に機能する」ことが指摘され
ています。より近年の研究でも、両者は異なる論理であるものの、使い分けがなされる
べき補完的関係にあることがいっそう強調されるようになりました。ただし、こうした
環境の変化に応じて意思決定に活用される論理が自然と変化するわけではなく、エフェ
クチュエーションとコーゼーションの両方を理解したうえで、意図的に切り替える能力が
重要であることも指摘されています。実際に、外部環境に対応して企業全体として優勢な
論理が切り替わるのか、それとも2つの論理が組織のなかの異なる領域やメンバー間で
併存しながら環境に適応していくのかを含めて、エフェクチュエーションとコーゼー
ションの組み合わせについては、今後の研究を通じてより理解が深まっていくことが
期待されます。
ただし一方で、豊富な経験を積むことにつれて、起業家自身はますますエフェクチュ
エーションに熟達し、好んで用いるようになることも想定されています。不確実性を
伴うチャレンジにおいては、環境の変化から目を離すことなく自ら操縦桿を握って対処
し続けることが重要であり、そうすることによって起業家は、熟練したパイロットの
ように、どのような不測の事態でもコントロールによって望ましい結果へと導いていけ
るようになるのです。
この続きは、次回に。
2026年1月14日
株式会社シニアイノベーション
代表取締役 齊藤 弘美