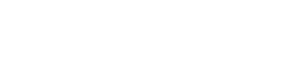田中角栄「上司の心得」④
第1章 「親分力」の磨き方
・「いつか総理にしたいな」と池田大作・創価学会会長
「親分力」とは何だろう。
上司としての度量、器を指す言葉として、これ以上、的確な言葉はない。
部下が曲がり角に立ち、切羽詰まっている。そんなとき、「心配するな。
人生は照る日曇る日」「オレに任せろ。泥はかぶってやる。
心配は無用」で、部下を窮地から脱出させてやる能力を指す。
加えれば、こうした上司に支えられ、窮地を脱出できた部下は、長らく
その恩義を忘れないのである。逆に上司が窮地に立ったとき、からだを
張ってでも支援の先頭に立ってくれるのは、こうした部下ということに
なる。
田中角栄が強大無比の人脈を構築し、長く絶大な権力を保持し得た背景は、
まさにこの「親分力」によるところが大きかった。
例えば、「角栄流」のこうした泥のかぶり方の好例に、巨大宗教団体・
創価学会が直面した「言論出版妨害事件」があった。
経緯はこうである。
創価学会が支持母体となる公明党は、それまで参院には進出していたが、
昭和42(1967)年1月の総選挙で初めて衆院に候補者を立て、一挙に25人の
当選者を出した。時の佐藤栄作政権下の自民党幹事長は福田赳夫(のちの
首相)だったが、この時点、福田と創価学会および公明党との間に特に
接点はなかった。
その2年後の総選挙では、自民党は福田に代わって田中角栄が3期目となる
幹事長に返り咲き、選挙の指揮を執った。結果、自民党は無所属当選者を
追加公認してじつに300議席を超える大勝となり、一方で公明党も前回の
倍近くの47人を当選させ、社会党に次ぐ野党勢力となった。
自民党としては、これだけ勢力の大きくなった公明党とのパイプづくりは
無視できないところに来たということでもあった。
そんな折、田中は当時の創価学会・池田大作会長(現・名誉会長)から、
東京・信濃町の創価学会本部に招かれ、初めて会談の機会を得た。
時に、田中はすでに近い将来、必ずや天下取りに動くだろうとの見方が
あった中で、党内外からはその勢いから「日の出の幹事長」との声が出て
いた。言うならば、会談はそんな田中と野党第2党に進出した公明党に
ニラミを利かせる池田会長の、今後の政局をにらんだハラの探り合いの
意味合いがあった。
このとき田中に同道したのは、秘書の早坂茂三(のちの政治評論家)だったが、
その早坂は、田中が帰りの車の中で池田会長の印象を次のように語ったと
筆者に明かしてくれたものだった。
「あれはしなやかな鋼だ」
これは田中特有の言い回しで、大宗教組織をまとめ上げ、索引する人物と
して、なるほど一筋縄ではいかぬ相当の「政治家」でもあることを見たと
いうことだった。そうした中で、田中と公明党との間で持ちつ持たれつの
関係が生じたのが、田中が5期目の幹事長時、昭和45年(1970)年の「言論
出版妨害事件」ということになる。
これは、その前年にジャーナリストの藤原弘達が、「創価学会を斬る」と
題した本を出版しようとしたことに端を発した。
藤原は公明党とその指示母体である創価学会との関係が、「政教分離」の
原則にもとるなどとし、文字通り創価学会を〝斬った〟のだった。
これに学会・公明党が反発、出版中止への圧力をかけたとされたものだった。
ここで、公明党側の窓口として、藤原へ出版待ったの説得にかかったのが、
衆院議員1回生にして同党委員長に就任していた竹入義勝だった。
じつは、時に、田中の女性問題や国有地払い下げに関する疑念を、公明党が
参院で追及する動きがあった。田中は自民党政調会長を辞した直後で、
すでに党内では〝ヤリ手〟として知られていた。
その田中は竹入に、こう言って深々と頭を下げたといわれている。
「できれば取り上げないで頂けないものか」
竹入は田中が有能で将来性に富んだ人物とにらみ、公明党の参院議員を
説得、質問に待ったを願い出たのだった。結果的に、これらの内容の質問は
中止された。ちなみに、これを契機に、田中と竹入の仲は「おれ」「おまえ
さん」で呼び合う肝胆相照らす間柄となっている。振り返れば、やがて
田中が首相となり、月刊誌「文藝春秋」で金脈・女性問題への疑念が明らかに
されたが、この兆はすでにその10年以上前に公明党内部の動きに見られたと
いうことである
● 度量
他人の言行をよく受けいれる、広くおおらかな心。「度量が広い」
● 切羽詰まる
ある事態などが間近に迫ってどうにもならなくなる。
身動きがとれなくなる。「―・って上司に泣きつく」
● 窮地
追い詰められて逃げ場のない苦しい状態や立ち場。
「窮地に陥る」「窮地を脱する」
● 恩義
報いなければならない、義理のある恩。「―を感じる」「―に報いる」
● 無比
他に比べるものがないこと。たぐいないこと。また、そのさま。無類。
無双。無二。「当代無比な(の)力士」「正確無比」「痛快無比」
この続きは、次回に。